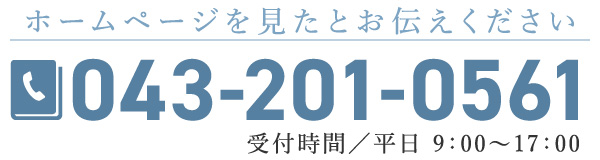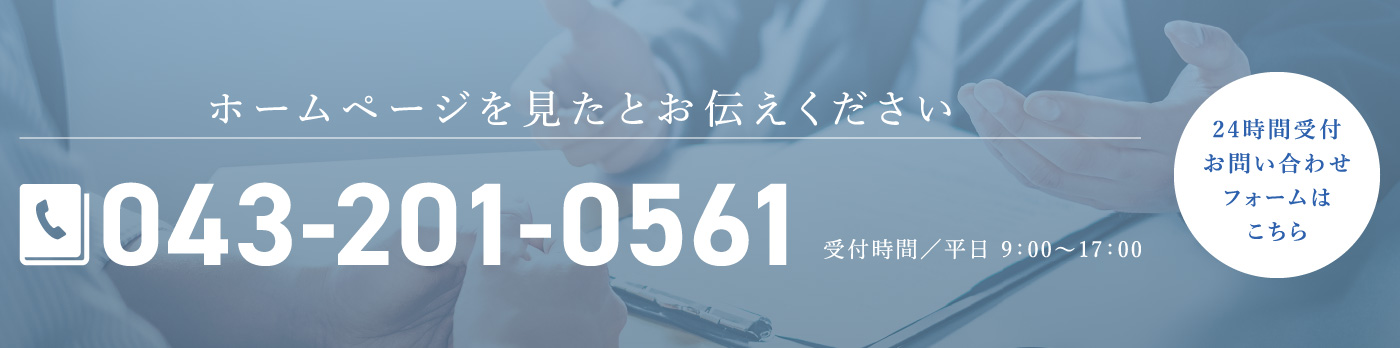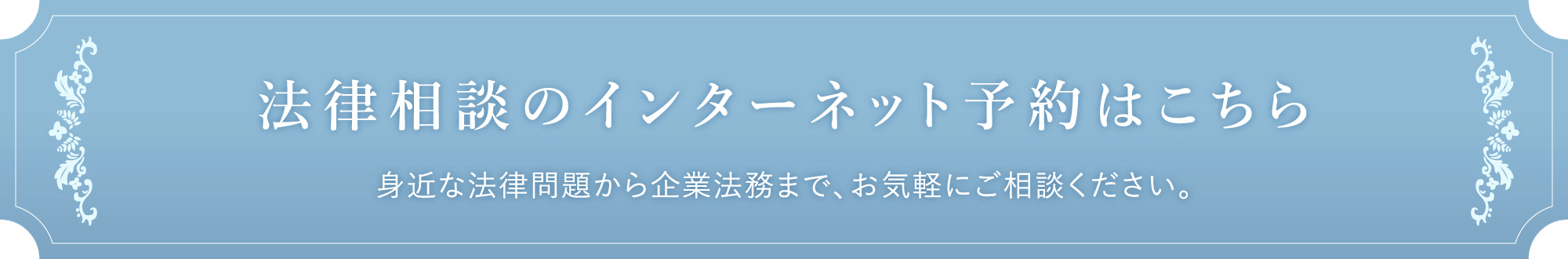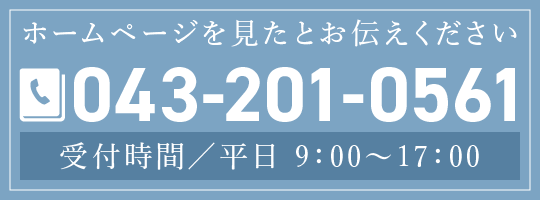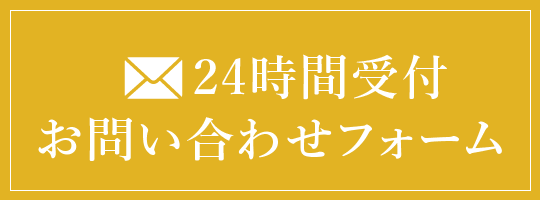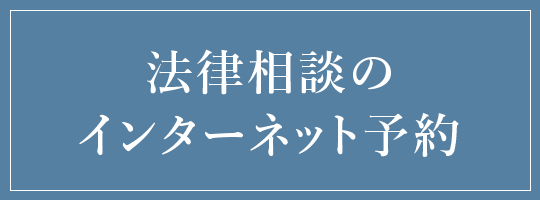- 「離婚のときには何を請求できるの?」
- 「財産分与って何?」
離婚の際に請求できるものの1つとして、財産分与があります。
このページでは財産分与についてご説明させていただきます。
1.財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚する際に、婚姻中に取得・維持された財産を清算するために分与を求めることです。
婚姻中、夫婦は互いに協力して生活を営み、財産を取得・維持します。たとえ一方が収入を得て、もう一方が家事や育児を担当していたとしても、その役割分担があったからこそ財産を築けたということになります。
つまり、目に見える収入だけでなく、家庭内での貢献も財産形成に寄与していると評価されます。
したがいまして、婚姻中に取得・維持された財産は、一方の名義であったとしても、実質上、夫婦の共同財産と考えられます。離婚時にこれを適切に分配することで、一方が不当に財産を独占することなく、公平な清算が実現されることになります。
2.財産分与の種類
財産分与には以下の3つの種類があります。
(1) 清算的財産分与
最も基本的な財産分与で、上記の財産分与のご説明は清算的財産分与のことです。
上記のとおり、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分配するものです。原則として2分の1ずつの割合で分けることが多いですが、財産形成への寄与度によって割合が変わることもあります。裁判例上、寄与度の判断は様々ですので、詳しくはご相談ください。
(2)扶養的財産分与
離婚後、一方の配偶者が経済的に自立することが困難な場合に、もう一方が扶養の意味で財産を分与するものです。例えば、専業主婦(夫)であったものが高齢や病気などの理由ですぐに収入を得ることが難しい場合などに認められることがあります。金銭ではなく、それまでに住んでいた住居の居住権が与えられることもあります。
(3)慰謝料的財産分与
離婚原因を作った配偶者が、相手方の精神的苦痛に対する償いとして行う財産分与です。本来、慰謝料と財産分与は別個の制度ですが、実務上は財産分与の中に慰謝料的要素を含めて解決することもあります。
実際の離婚では、これらの要素が複合的に考慮されて財産分与の内容が決定されることが多いです。
具体的な分与の内容や割合については、個々のケースによって異なります。今後施行される民法の条文の表現を借りますと、
「家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」(民法768条3項)
ということになります。
3.財産分与の対象になるものとならないもの
(1)対象になるのは特有財産以外
上記のとおり、財産分与は原則として婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分配するものですので、財産分与の対象になるものは「当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産」(民法768条3項)ということになり、ならないものは「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」(特有財産)(民法762条1項)ということになります。
「婚姻中自己の名で得た財産」は、その取得対価も自己のものであることが立証されない限り、共有の推定が働きますので、婚姻中に得た収入で取得した財産は一方の単独名義であっても財産分与の対象になります。
なお、扶養的財産分与は財産の清算ではないので、特有財産も考慮して分与の内容が定められます。
(2)特有財産とは
財産分与の対象となる財産か否か、すなわち、特有財産か否かは、実務でもよく争われます。
一般的には、
- 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産
- 婚姻後であってもその親族からの贈与、相続などによって取得した財産
- 夫婦の合意により特有財産とした専用財産
の3つは特有財産とされますが、特有財産か否か争いがある場合は特有財産と主張する者がこれを立証する必要があり、立証できない場合には共有財産として分与の対象になります。
特有財産であっても、夫婦の協力があったことにより維持されてきたものは財産分与の対象になります。例えば、夫婦の一方が婚姻前に取得した不動産のローンを婚姻後の収入で支払った場合、同居期間中の住宅ローンの返済分に相当する部分は夫婦の実質的共有財産にあたるとした裁判例があります(東京高裁H29.7.20決定)。
特に問題になりやすいものとしては預貯金があります。
婚姻前からの残高がある場合、通常は婚姻前からの残高に婚姻中の収入が混じり合っているので、全部が特有財産として扱われることはないと思われますが、婚姻中に入金が全くない場合や婚姻前からの定期預金は特有財産となる可能性があり、ケースバイケースです。
(3)その他対象にならないもの
なお、婚姻破綻時(通常は別居時)に存在しない財産は、過去に存在したとしても原則として財産分与の対象にはなりません。また、婚姻破綻時後に取得された財産は離婚確定前に取得されたものであっても財産分与の対象にはなりません。
4.弁護士に相談・依頼するメリット
以上、財産分与についてご説明させていただきましたが、財産分与について弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
(1)専門的な法的アドバイスが得られる
前記のように財産分与は法律的に複雑な問題です。このページでは書ききれませんが、財産として保険や投資信託があったり、退職金制度がある場合もありますし、住宅ローン付の不動産がある場合もあります。また、過去の婚姻費用も財産分与として考慮されます。
弁護士は民法の規定や裁判例に基づいて、あなたのケースに適した分与方法や割合についてアドバイスできます。特に特有財産と共有財産の区別、寄与度の評価などは専門知識が必要です。
財産分与を請求された場合には、特有財産であるとの立証や、寄与度が2分の1ではない旨の立証も必要となります。
(2)交渉の代理が依頼できる
感情的になりがちな離婚協議において、弁護士は冷静に交渉を進めることができます。相手方と直接話し合うストレスも軽減されます。
(3)書類作成と手続きのサポート
財産分与の条項を含む離婚協議書や、離婚調停申立ての際の調停申立書など、法的に有効な書類の作成を支援してもらえます。また、調停や訴訟の場面でも法的根拠に基づく適正な財産分与の請求が可能です。
以上のとおり、財産分与で後悔しないためには弁護士に相談・依頼するメリットは少なくありませんので、離婚をお考えの際には弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
当事務所では離婚のご相談は初回1時間まで無料ですので、費用は気にせずまずはお気軽にお問い合わせください。