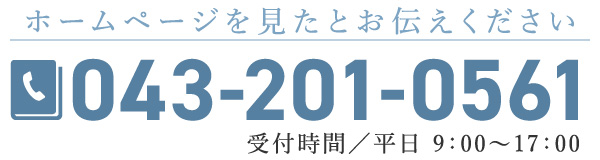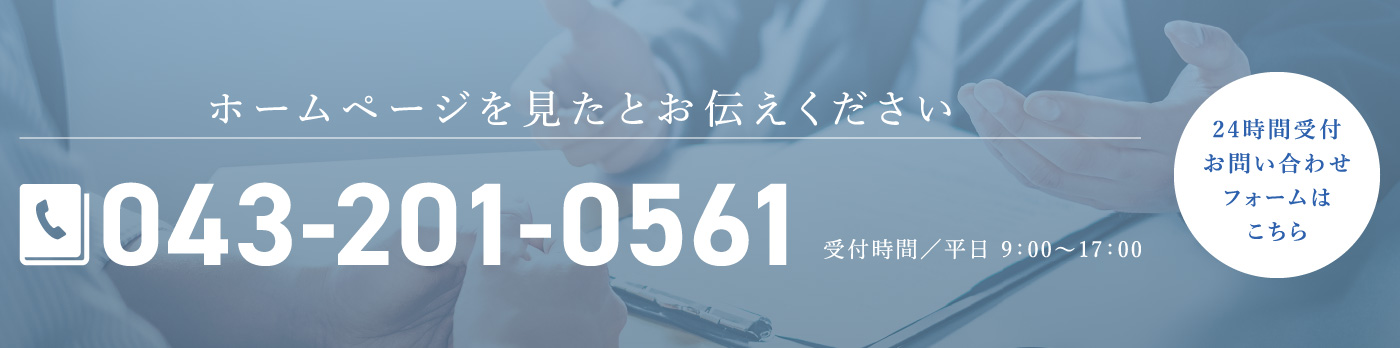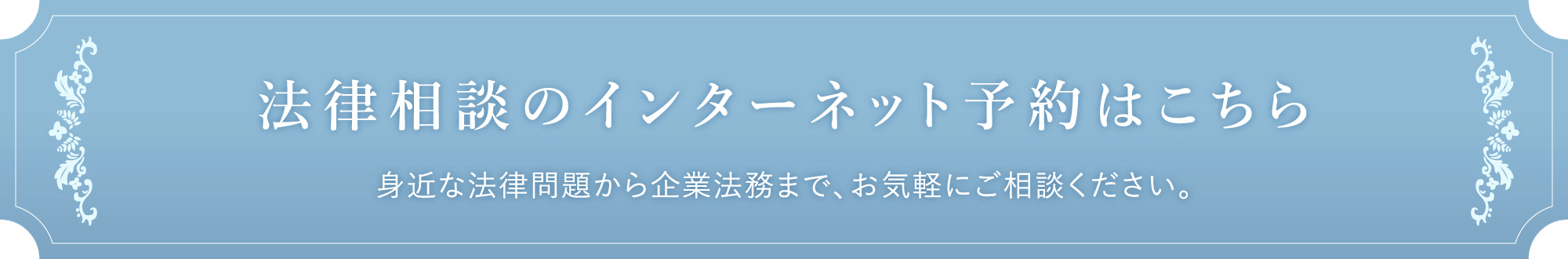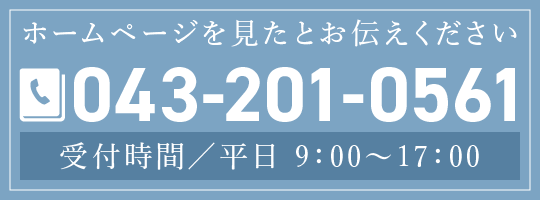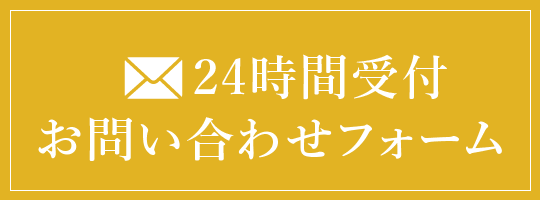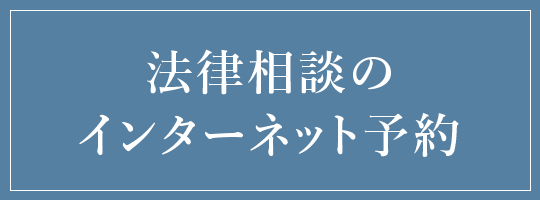- 「養育費はいくら請求できるの?」
- 「養育費を支払ってもらえなくなったときはどうすればいいの?」
離婚によってお子さんを監護養育する側の親は、監護養育していない側の親に対して養育費を請求することができます。
このページでは養育費についてご説明させていただきます。
1.養育費とは
養育費とは、民法という法律で「子の監護に要する費用」と定められている(民法766条)、子供を監護養育するために必要な費用のことです。
「監護」とは、子供の身の回りの世話を現実に行うことです。つまり、養育費とは、子供の身の回りの世話を現実に行っている親から、行っていない親に対して請求できる子育てのための費用ということになります。
民法では、子供の父母が離婚をするときは子の監護に要する費用の分担等を協議で定めることとし(民法766条1項)、協議が調わないときや協議をすることができないときには家庭裁判所が定めることとしています(民法766条2項)。
2.養育費の計算方法
(1)裁判所での計算方法
養育費の額につき、どの程度が適正かというのは各家庭の事情によって異なるとは思いますが、裁判所で使われている計算方法が参考になります。裁判所では、標準的算定方式及びこれに基づく算定表が、養育費や婚姻費用の計算に用いられています。ちなみに、婚姻費用とは、別居中、離婚成立までの間に請求できる費用で、子供がいる場合には養育費も含まれています。
算定表では、父母それぞれの収入と子供の人数及び年齢をもとにして簡易迅速に養育費の額が計算できるようになっています。通常はこの算定表をもとにして養育費の額が定められており、算定表を超える額の算定をするには算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られるとされています。算定表は以下の裁判所のサイトで見ることができます。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
なお、当事務所では、父母双方が給与所得者で標準的な事例の場合には、算定表のもととなっている数式を用いて算定表より細かく養育費の額を計算しています。
(2)収入の認定方法
算定表では父母それぞれの収入を認定する必要があります。給与所得者の場合には、通常、源泉徴収票や所得証明書を用いて認定します。ちなみに、当事務所が扱った事件の1つでは、親族の経営する会社に勤務していた相手方が親族の協力を得て収入額を少なくした源泉徴収票を出してきたことがありましたが、あらかじめこちら側が所得証明書を取得していたので嘘を見破ることができました。
自営業者の場合には確定申告書の課税所得によりますが、そのままの数字では現実に支出されていない費用も控除されてしまっているので、所得金額から社会保険料のみを控除し、青色申告特別控除と専従者給与額の合計額を加算した額を収入とします。
経費の水増しには注意する必要があります。減価償却費を控除するか否かはケースバイケースです。所得が信用できない場合には、生活費の支出額をもとに少なくともその分の収入はあったと認定することもあります。また、場合によっては、賃金センサスという平均賃金の統計資料を用いることもあります。
無職の場合でも、働く能力がある場合には収入はゼロとはされず、賃金センサスを用いて収入を認定することがあります。専業主婦であった者も、少なくともパートタイムとしての労働は可能として収入を認定される可能性がありますが、乳幼児がいてその監護養育のために働けない場合などには、概ね子が3歳程度までは無収入でもやむを得ないとされることが多いです。
なお、養育費をもらう側の生活保護費、児童手当、児童扶養手当は収入として扱われません。また、実家からの援助も収入に加算されません。
3.養育費の増額・減額
一度決まった養育費を様々な事情で変更(増額または減額)したい場合があります。
養育費の額が初めから不当であって是正を要する場合と、その後の事情の変更により是正の必要が生じた場合には、養育費の増額または減額が認められることがあります。
事情の変更といっても、すべての事情変更が養育費の増額または減額の理由として認められるわけではありません。養育費を取り決めた当時には予見できなかった事情変更で、かつ、事情変更が生じたことが当事者の責任ではないことが必要です。
最も多く主張される事情変更は収入の減少です。
一般的には、予想外の収入の減少は事情変更ということができますが、時間外手当や期末手当の変動は予想の範囲内であり、ある程度の業績の変動も予想の範囲内となります。予想外の事情変更の典型例としては、自らの責任によらない退職や勤務先の倒産などがあります。
養育費をもらう側の収入の増加も養育費減額の理由となり得ますが、払う側の収入が減少したわけではないので、よほど多額の増加でない限りは減額の理由とはなりません。
養育費を払う側が再婚した場合、養育費を取り決めた当時にはすでに交際していたなどの事情がなければ、事情変更になり得ます。養育費をもらう側が再婚した場合で再婚相手が子と養子縁組をした場合には、再婚相手と養育費をもらう側との収入を合せた額が子を扶養するに足りないなどの事情がない限り、養育費の支払義務がなくなります。
4.養育費を支払ってほしいとき・支払われなくなったとき
(1)まずは話合いをする
養育費を請求するには裁判手続による必要はありません。相手方に養育費を請求する旨を伝え、双方の話合いにより養育費の額や毎月の支払日等を決めて、養育費を支払ってもらうことになります。話合いがついたときには、後述の理由により、公証役場で公正証書を作成することをお勧めいたします。
(2)話合いがつかないとき
話合いがつかないときには、養育費を求める調停を家庭裁判所に申し立てることになります。申し立てる家庭裁判所は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。離婚の調停に付随して申し立てることもできます。
調停では、裁判所が中立な第三者として間に入り、話合いが行われます。合意ができれば調停が成立し、養育費の額や支払期日、支払方法、子が何歳になるまで養育費を支払う義務があるかなどが記載された調停調書が作成されます。
(3)調停でも解決できないとき
調停でも話合いがつかない場合、離婚が成立していなければ離婚訴訟に付随して養育費を請求することになります。したがいまして、離婚が成立していない場合、養育費を請求するためには離婚訴訟を提起する必要があります。離婚がすでに成立していれば、養育費の調停が不成立になったときには自動的に裁判所の審判手続に移りますので、あらためて審判の申立てをする必要はありません。
審判手続では、前述の標準的算定方式及びこれに基づく算定表に基づき、お互いの収入や特殊事情を考慮して養育費の額や支払期日、子が何歳になるまで養育費を支払う義務があるかなどを裁判所が強制的に決めます(審判)。審判の際、裁判所は審判書を作成します。この審判に対しては不服申立てを行うことができますが、不服申立てが行われなければ審判は確定します。
離婚訴訟に付随して養育費を請求した場合には、離婚を認める判決と同時に裁判所が養育費の額や支払期日、子が何歳になるまで養育費を支払う義務があるかなどを強制的に決めます。判決の際には判決書が作成されます。この判決に対しては不服申立てを行うことができますが、不服申立てが行われなければ判決は確定します。
(4)養育費が支払われないとき
審判や判決で養育費が強制的に決まっても、不誠実な相手方の場合、養育費を支払ってこないことがあります。また、当事者双方の合意や調停で養育費の支払いが決まっても養育費を支払わない者もいますし、途中で支払わなくなる者もいます。この場合、養育費を支払うよう裁判所から相手方に対して督促してもらったり、命令してもらったりすることを検討します。また、相手方の財産を差し押さえることも検討します。
ア 養育費を支払うよう裁判所から相手方に対して督促してもらう制度を履行勧告と言います(家事事件手続法289条及び人事訴訟法38条)。
この制度を利用できるのは、調停、審判または訴訟によって養育費の支払いが決まった場合に限られますので、裁判手続を利用せずお互いの話合いのみで養育費を決めたときは公正証書を作成していたとしても利用できません。履行勧告では、裁判所が相手方に通知するなどして養育費の支払いを督促しますが、相手方がそれにも従わなかったとしても強制力はありません。
イ 養育費を支払うよう裁判所から相手方に対して命令する制度を履行命令と言います(家事事件手続法290条及び人事訴訟法39条)。
上記の勧告と命令との違いは、養育費の場合、命令に応じなかった相手方に10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科せられる可能性があることです。過料が科せられるという意味で心理的強制力があると言えます。
ウ 相手方の財産を差し押さえる手続を、強制執行手続と言います。差し押さえる財産としては不動産も考えられますが、一番多いのは給与と預貯金です。
強制執行手続を裁判所に申し立てるためには、少なくとも債務名義と呼ばれるものが必要であり、前述の公正証書、調停調書、審判書、判決書がそれにあたります。したがいまして、裁判手続を利用せずお互いの話合いのみで養育費を決めたときは、公正証書を作成していない限り、あらためて裁判所に調停や訴訟を申し立てる必要があります。
相手方の給与を差し押さえるには、相手方の勤務先がわからなければなりません。
裁判所を通じて市区町村や日本年金機構等から勤務先情報を取得する手続もありますが(第三者からの情報取得手続)、先に財産開示手続を行っておく必要があるため、給与の差押のためには、財産開示手続、第三者からの情報取得手続及び給与差押手続の3つの手続を行う必要があります。
相手方の勤務先がわかっていれば給与差押手続のみで相手方の毎月の給与の2分の1まで差し押さえることができます。
相手方の預貯金を差し押さえるためには、銀行名と支店名がわからなければなりません。裁判所を通じて銀行や証券会社から預貯金情報を取得する手続もありますが(第三者からの情報取得手続)、銀行や証券会社ごとにしか取得はできないので、取得先の銀行や証券会社が1個増えるごとに4000円の予納金が必要になります。
なお、預貯金情報の取得の場合、先に財産開示手続を行っておく必要はありませんが、少なくとも財産調査結果報告書の作成は必要です。
以上のとおり、養育費を支払ってもらうためには、法定養育費を除いて、父母の話し合いまたは裁判手続が必要になります。弁護士は養育費の実務に精通しておりますので、相手方との間で実務を踏まえた交渉が可能ですし、裁判手続の専門家でもあります。養育費でお悩みなら、まずはお気軽にお問い合わせください。
注:以上で記載したことは現時点での話であり、令和8年4月1日からは変わる部分があります。
まず、一定の養育費(現時点では子供1人当たり毎月2万円との案が出されています。)については、父母の話合いがなくても離婚の日から養育費を請求することができ、債務名義がなくても相手方の財産を差し押さえる強制執行手続をすることができるようになります(法定養育費)。
また、前述のとおり、現時点では相手方の勤務先がわからない場合には財産開示手続、第三者からの情報取得手続及び給与差押手続の3つの手続を行う必要がありますが、令和8年4月1日以降は、財産開示手続または第三者からの勤務先情報取得手続を申し立てると給与差押手続も申し立てたとみなされるため、申立てが1回で済むようになります。