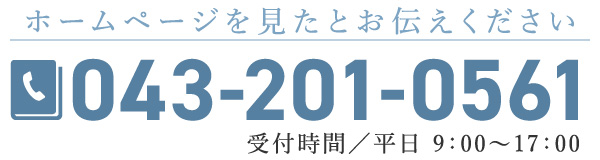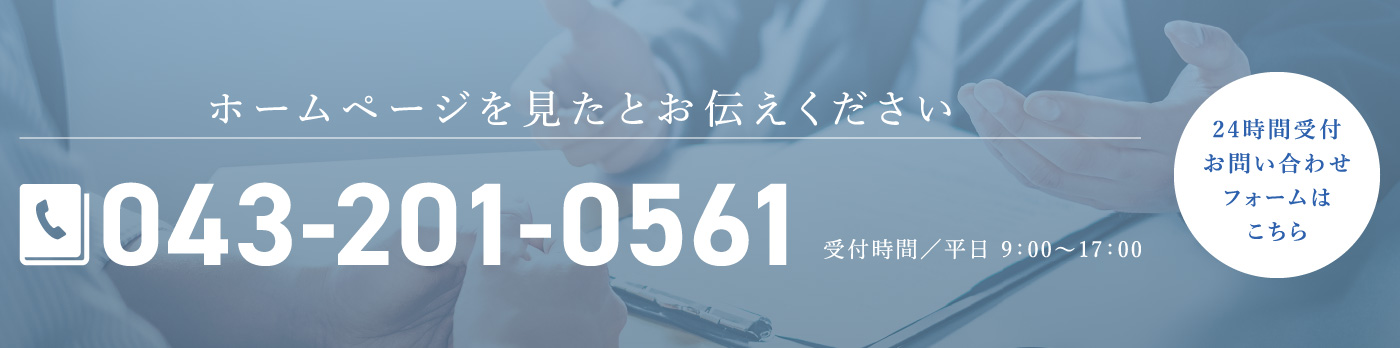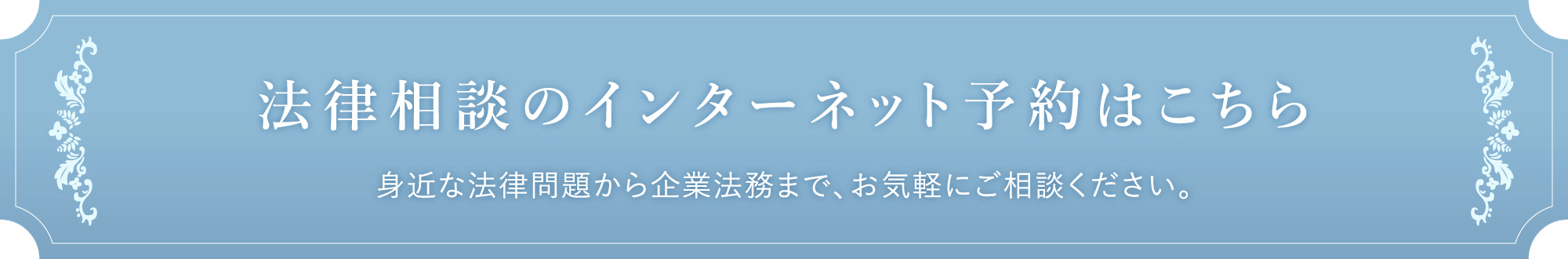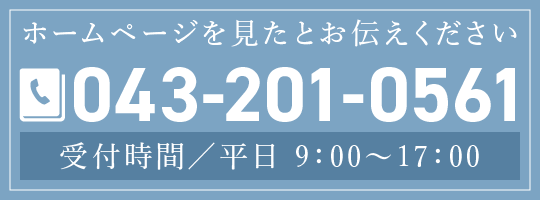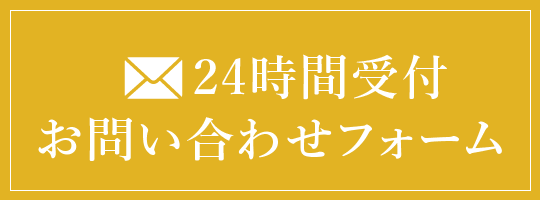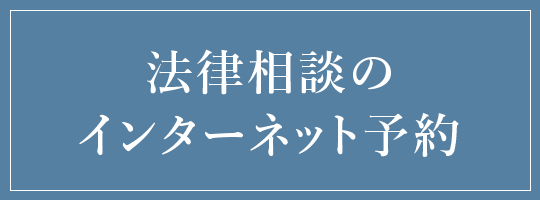突然の「症状固定」「治療費打ち切り」…お一人で悩んでいませんか?
交通事故に遭われ、心身ともにお辛い中、ようやく治療に専念できると思っていた矢先…。
突然、保険会社の担当者から「そろそろ症状固定ですね」「来月で治療費の支払いを打ち切ります」といった連絡を受け、頭が真っ白になってしまったのではないでしょうか。
「まだ痛みやしびれが残っているのに…」
「治療をやめたら、この症状はどうなってしまうのだろう?」
「保険会社が言うのだから、従うしかないのだろうか…」
先の見えない不安と、誰にも相談できない孤独感に苛まれているかもしれません。
ですが、どうかご安心ください。保険会社のその言葉に、安易に従う必要はまったくありません。
この記事では、交通事故の被害者の方々が直面する「症状固定」と「治療費打ち切り」の問題について、法律の専門家である弁護士が、その本当の意味と、あなたが今取るべき正しい対処法を、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を冷静に把握し、次に何をすべきかが明確になっているはずです。お一人で抱え込まず、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。
まず知るべきこと:「症状固定」と「治療費打ち切り」の本当の意味
保険会社の担当者から告げられる「症状固定」や「治療費打ち切り」という言葉は、非常に重く、決定的なものに聞こえるかもしれません。
しかし、その言葉の法的な意味を正しく理解することが、冷静に対応するための第一歩です。
「症状固定」を決めるのは保険会社ではなく医師です
最も重要なポイントは、「症状固定」の時期を最終的に判断するのは、加害者側の保険会社ではなく、あなたの治療を続けてきた主治医であるということです。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても、症状の大幅な改善が見込めない状態」を指す医学的な判断です。
もちろん、痛み止めを処方してもらったり、リハビリを続けたりすることで症状が安定することはありますが、ケガが完治したわけではありません。
保険会社は、過去の事例から「むちうちなら3ヶ月」「骨折なら6ヶ月」といった社内基準に基づき、機械的に症状固定を打診してくることがよくあります。
しかし、それはあくまで保険会社の都合であり、あなたの実際の症状に基づいた医学的判断ではありません。
主治医が「まだ治療による改善の可能性がある」と判断している限り、安易に症状固定に同意する必要はないのです。
「治療費打ち切り」=治療終了ではありません
「治療費を打ち切ります」という通告も、非常に強い言葉で不安を煽りますが、これも正確に理解する必要があります。
これはあくまで、保険会社が病院に直接治療費を支払うサービス(一括対応)を停止します、という意味合いに過ぎないのです。
もし主治医がまだ治療の必要性を認めているのであれば、あなたは治療を続ける権利があります。
保険会社が一括対応を停止した後も、ご自身の健康保険などを利用して治療を続け、そこで立て替えた治療費は、後日、示談交渉や裁判を通じて加害者側に請求することが可能です。
ですから、「治療費打ち切り」を告げられたからといって、必要な治療を諦める必要は決してありません。
症状固定・治療費打ち切りを告げられた後の3つの選択肢
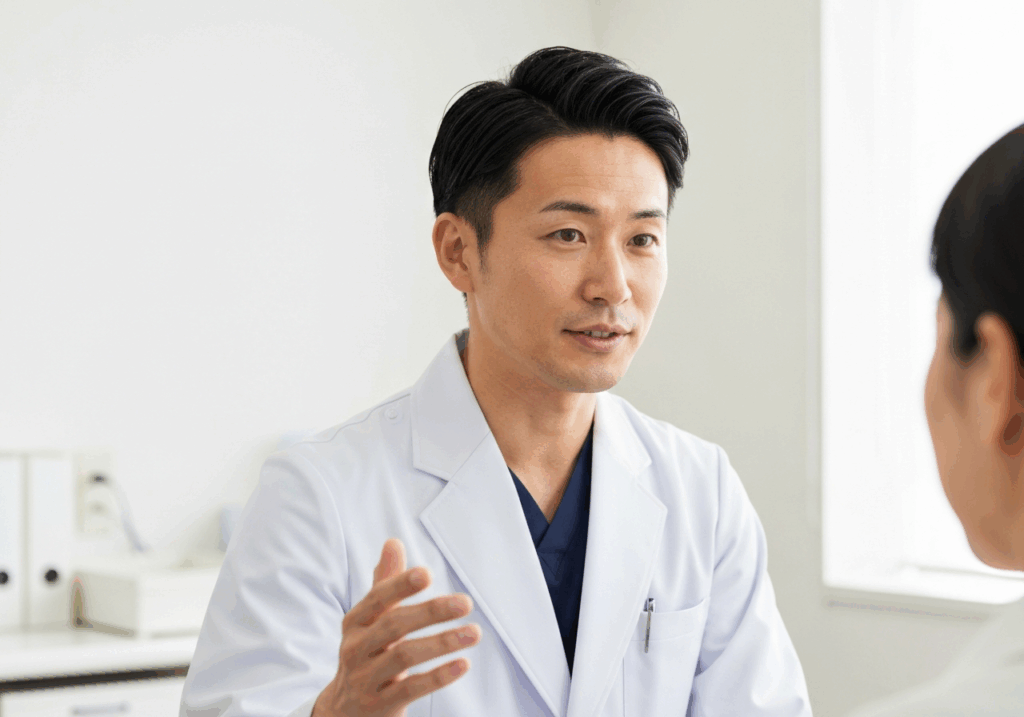
保険会社から症状固定や治療費打ち切りを打診されたとき、具体的にどのような行動を取ればよいのでしょうか。
ご自身の状況に合わせて、主に3つの選択肢が考えられます。
選択肢1:医師と連携し、治療の継続を交渉する
まだ痛みやしびれがあり、主治医も治療による改善の余地があると考えている場合は、保険会社に対して治療期間の延長を交渉すべきです。
その際、単に「まだ痛いんです」と感情的に訴えるだけでは、なかなか聞き入れてもらえません。
重要なのは、主治医に協力してもらい、「なぜ治療が必要なのか」という医学的な根拠を示すことです。
具体的には、今後の治療計画や症状改善の見込みなどを記載した診断書を作成してもらうのが非常に有効です。このような客観的な証拠を提示することで、保険会社も交渉に応じざるを得なくなるケースが多くあります。
もちろん、こうした保険会社との交渉は弁護士が代理人として行うことで、よりスムーズに進められる可能性が高まります。
選択肢2:一旦自費で治療を続け、後で請求する
保険会社との交渉が難航し、治療費の支払いを打ち切られてしまった場合でも、医師が必要だと判断する限りは治療を続けましょう。
その際、自由診療のままでは自己負担が大きくなってしまうため、必ずご自身の健康保険を利用してください。
健康保険を利用すれば、自己負担は原則3割(年齢や所得による)に抑えられます。
そして、治療のために支払った自己負担分や、通院交通費などは、すべて記録し、領収書を保管しておきましょう。
これらの費用は、最終的な示談交渉の際に、治療の必要性や相当性が認められれば、他の損害賠償金とあわせて加害者側に請求することができます。
選択肢3:症状固定を受け入れ、後遺障害等級認定に進む
主治医と相談した結果、「これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない」という判断に至った場合は、症状固定を受け入れ、次のステップに進むことになります。
それは、残ってしまった症状(後遺症)に対する正当な補償を求める「後遺障害等級認定」の手続きです。
後遺障害が認定されると、治療費や通院慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」や、後遺症によって将来の収入が減少することへの補償である「逸失利益」を請求できるようになります。
この後遺障害等級が認定されるかどうか、そしてどの等級(1級~14級)に認定されるかによって、最終的に受け取れる賠償金の額が数百万円、時には数千万円単位で変わることもあります。
これは、交通事故の賠償手続きにおいて最も重要な分岐点と言っても過言ではありません。
弁護士への相談が、あなたの未来を大きく変える理由

症状固定や治療費打ち切りを告げられたタイミングは、まさに弁護士への相談を検討すべき絶好の機会です。
専門家である弁護士に依頼することで、あなたが得られるメリットは、決して小さなものではありません。
保険会社との交渉窓口となり、精神的負担を軽減
保険会社の担当者とのやり取りは、それ自体が大きな精神的ストレスになります。特に、お身体が辛い中で、専門用語を並べ立てられたり、高圧的な態度を取られたりすれば、心身ともに疲弊してしまいます。
弁護士にご依頼いただければ、私たちがすべての交渉窓口となります。あなたは保険会社と直接話す必要がなくなり、煩わしいやり取りから解放され、安心して治療に専念することができます。
この精神的な負担の軽減は、依頼者の方々が最も喜ばれる点の一つです。
医学的証拠に基づき、適正な後遺障害等級認定をサポート
前述の通り、後遺障害等級認定は賠償額を大きく左右する重要な手続きですが、これは非常に専門的です。
単に「後遺症が残った」と主張するだけでは認定されず、カルテやMRI・CT画像、各種検査結果といった医学的な証拠によって、症状の存在や事故との因果関係を客観的に証明しなければなりません。
私たち弁護士は、これまでの経験に基づき、認定に必要な検査が適切に行われているか、後遺障害診断書に記載すべき重要な点(自覚症状と、それを裏付ける医学的な他覚所見など)が漏れていないかを精査します。
必要であれば、医師に意見書作成の協力をお願いすることもあります。専門家が介入することで、本来認定されるべき等級を、より確実に獲得できる可能性が高まります。
「弁護士基準」での交渉で、賠償額の大幅増額を目指す
交通事故の慰謝料には、実は3つの異なる算定基準が存在します。保険会社が当初提示してくる金額は、最も低額な「自賠責基準」か、それに少し上乗せした程度の「任意保険基準」であることがほとんどです。
しかし、弁護士が介入して交渉する場合、過去の裁判例の蓄積から作られた、最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」を用いて請求します。
例えば、むちうちで6ヶ月通院した場合の傷害慰謝料は、自賠責基準と裁判基準では金額が大きく異なる場合があります。詳しくは「傷害慰謝料の自賠責基準と裁判基準」のページもご覧ください。
弁護士に依頼することで、あなたが受け取るべき正当な賠償額が、数十万円から数百万円以上増額されるケースも決して珍しくありません。
まずはご相談でお話をお聞かせください。早ければ早いほど、私たちがご提供できるサポートの幅も広がります。
早川法律事務所の解決事例
当事務所では、これまで多くの交通事故被害者の方々からご相談をお受けし、問題解決のサポートをしてまいりました。
ここでご紹介する解決事例は、個人が特定されないよう内容を一部変更して掲載しております。
事例1:治療終了宣告から一転、後遺障害認定で賠償額が大幅増額
ご相談にいらしたAさんは、加害者側の保険会社から「来月で治療は終わりにしてください」と一方的に告げられ、途方に暮れていました。
Aさんにはまだ手首の痛みが残っておりました。
私はAさんのお話を詳しく伺い、すぐに主治医に後遺障害診断書の作成を依頼するよう助言し、後遺障害の申請手続きを行いました。
その結果、Aさんの症状は「局部に頑固な神経症状を残すもの」などとして後遺障害等級併合11級が認定されました。
後遺障害診断書の作成により、後遺障害慰謝料や逸失利益を含め、当初の提示額から賠償額を大幅に増額させることができ、Aさんにも大変ご満足いただけました。
事例2:裁判で症状固定時期を争い、治療費・慰謝料が増額
Bさんのケースでは、保険会社が「事故から6ヶ月後には症状固定していたはずだ」と主張し、それ以降の治療費や通院慰謝料の支払いを拒否していました。
しかし、Bさんは実際には半年以上にわたって痛みに耐えながら治療を続けていたのです。
私たちは、Bさんの主張が正当であることを証明するため、裁判に臨みました。
そして、診療記録(カルテ)や各種検査結果をすべて証拠として取り寄せ、症状が一貫して継続していたこと、治療によって症状が少しずつ改善していたことなどを丁寧に主張・立証していきました。
最終的に、裁判所は私たちの主張を認め、保険会社が主張するよりも遅い、Bさんが実際に治療を終えた時期を症状固定日と認定しました。
これにより、Bさんは支払いを拒否されていた期間の治療費全額と、通院期間に応じた正当な通院慰謝料を受け取ることができました。
まとめ:納得できない「症状固定」は弁護士にご相談ください

この記事では、交通事故における「症状固定」と「治療費打ち切り」の問題について解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度お伝えします。
- 「症状固定」を決めるのは保険会社ではなく、あなたの主治医です。
- 「治療費打ち切り」は治療の終了を意味するものではありません。
- 納得できない場合は、医師と連携して交渉したり、健康保険で治療を続けたりする選択肢があります。
- 後遺症が残る場合は、「後遺障害等級認定」の手続きが極めて重要です。
- 弁護士に相談することで、精神的負担が減り、賠償額が大幅に増える可能性があります。
保険会社から症状固定や治療費打ち切りを告げられたとき、決して一人で判断したり、諦めたりしないでください。
その判断が、あなたの今後の人生を大きく左右する可能性があるからです。
私たち早川法律事務所は、千葉市で15年以上にわたり、多くの交通事故被害者の方々のサポートをしてまいりました。
代表弁護士の早川 哲弘(千葉県弁護士会所属)が、すべての相談に直接対応し、あなたの状況を丁寧にお伺いした上で、豊富な経験に基づいた最善の解決策をご提案します。
保険会社の対応に少しでも疑問や不安を感じたら、どうかお一人で悩まず、私たち専門家にご相談ください。