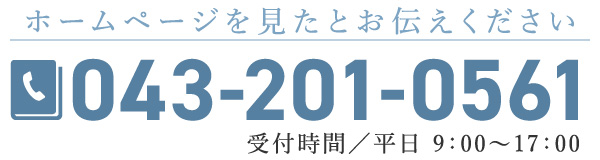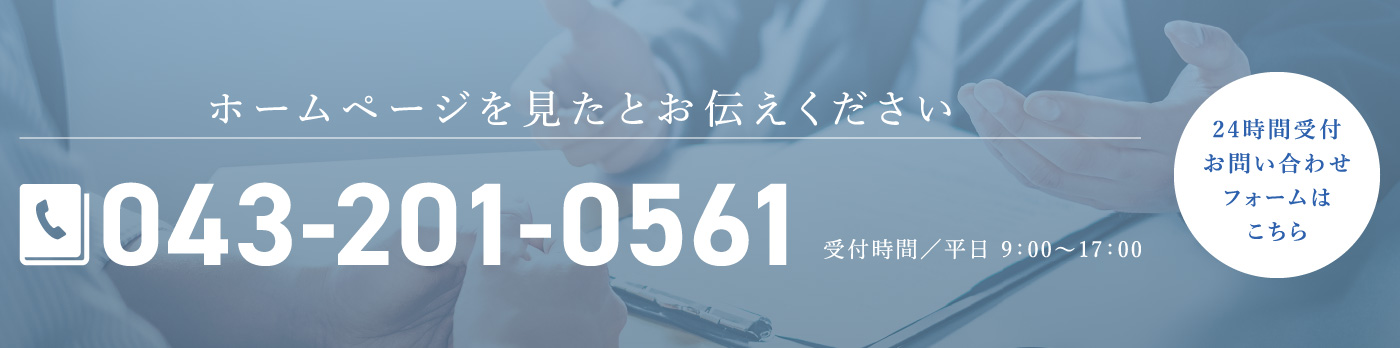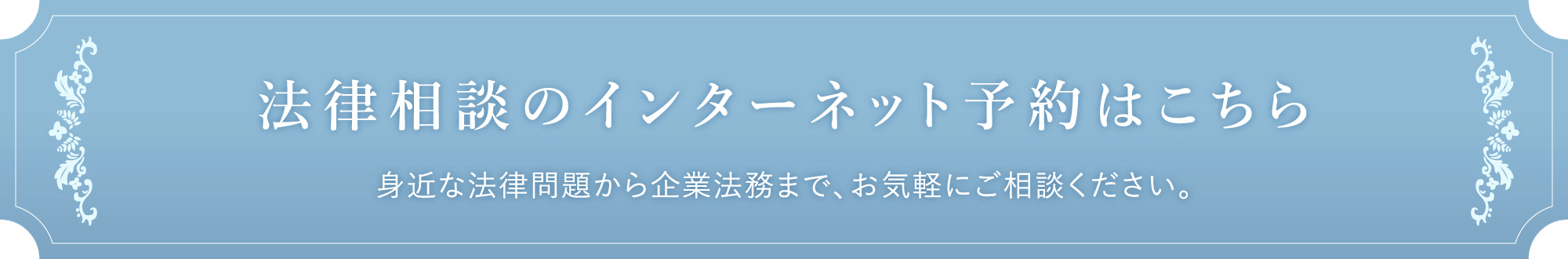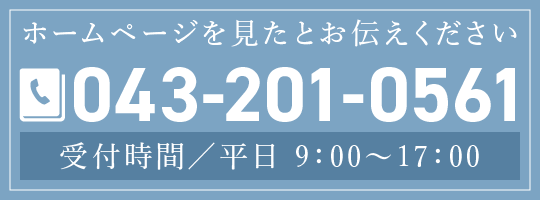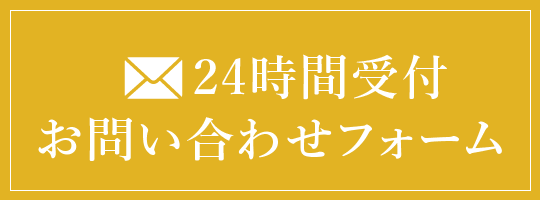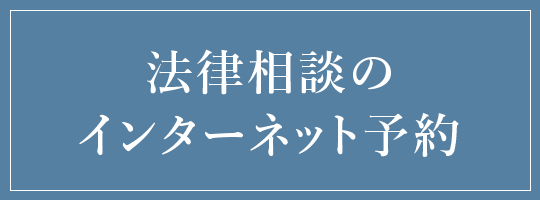自己破産における「同時廃止」とは?管財事件との違い
借金の返済が困難になり、自己破産を考え始めたとき、「同時廃止」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
自己破産の手続には、実は「同時廃止事件」と「管財事件」という2つの種類があり、どちらになるかで手続の内容や期間、費用が大きく変わってきます。
ここでは、まずこの2つの違いについて、分かりやすくご説明します。
同時廃止:財産がない場合に行われるシンプルな手続
同時廃止とは、自己破産を申し立てる方に、債権者(お金を貸した側)に配当するほどのまとまった財産がない場合に適用される、比較的シンプルな手続です。
名前のとおり、裁判所が「破産手続を開始する」と決めたのと「同時」に、財産を調査したりお金に換えたりする手続きを「廃止(終了)」します。
つまり、財産を処分する手続が省略されるため、手続にかかる期間が短く、裁判所に納める費用も安く抑えられるという大きなメリットがあります。
多くの個人の自己破産事件は、この同時廃止に該当します。
管財事件:一定の財産がある場合や調査が必要な場合の手続き
一方、管財事件は、自己破産を申し立てる方に一定額以上の財産がある場合や、借金の理由などに調査が必要な場合に適用される、より丁寧な手続です。
裁判所によって「破産管財人」という弁護士が選任され、この破産管財人が申立人の財産を調査・管理し、お金に換えて債権者に公平に配当します。
また、借金の経緯に免責を認められない可能性のある事情(免責不許可事由)がないかどうかも調査します。
手続が複雑になるため、同時廃止に比べて期間が長くなり、破産管財人の報酬として裁判所に納める費用(引継予納金)も高額になります。
あなたがどちらに該当するかの判断基準
ご自身のケースが同時廃止になるか、それとも管財事件になるか、気になる方も多いでしょう。最終的には裁判所が判断しますが、一般的に同時廃止になりやすいのは、以下の条件を満たす場合です。
- 処分すべき財産がないこと
具体的には、現金・預貯金、保険の解約返戻金、自動車、不動産などの個別の財産の価値が20万円未満である場合が目安となります(裁判所の運用によって基準は異なります)。 - 免責不許可事由の疑いがないこと
ギャンブルや浪費が借金の主な原因である、財産を隠している、特定の債権者だけに返済した(偏頗弁済)などの事情がないことが求められます。
これらの基準はあくまで目安です。ご自身の状況でどちらになるか正確に知りたい場合は、一度弁護士にご相談いただくのが確実です。
【弁護士に依頼した場合】自己破産(同時廃止)の手続の流れと期間

それでは、実際に弁護士に依頼した場合の、同時廃止の手続の流れをステップごとに見ていきましょう。
STEP1:弁護士への相談・依頼
まず、法律事務所に相談の予約をとり、弁護士と面談します。現在の借金の状況、収入や財産、借金の経緯などをお伺いし、自己破産が最善の方法か、同時廃止で進められる見込みはどのくらいかなどを検討します。
ご相談の際は、借入先の一覧や収入がわかる資料(給与明細など)をお持ちいただくと、より具体的なアドバイスが可能です。方針にご納得いただけましたら、委任契約を結びます。
弁護士に依頼すると、すぐに各債権者へ「受任通知」という手紙を送付します。この通知が届けば、貸金業者からの取り立てや督促がストップします。
精神的な負担が大きく軽減される、非常に大きなメリットです。

STEP2:自己破産申立ての準備
次に、裁判所に提出する申立書を作成する準備をし、必要な書類を集めます。集めていただく書類は多岐にわたりますが、千葉地裁の場合、主なものは以下のとおりです。
- 住民票
- 給与明細書(申立前2か月分)
- 源泉徴収票、課税証明書(過去2年分)
- 預金通帳のコピー(過去2年分)
- 保険証券、車検証、不動産登記簿謄本など財産に関する資料
書類集めは少し大変に感じられるかもしれませんが、当事務所の弁護士がリストをお渡しし、集め方を丁寧にご案内しますのでご安心ください。

STEP3:裁判所への自己破産申立て
すべての書類が揃ったら、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行います。この申立て手続は弁護士が代理人として行いますので、ご本人が裁判所へ行く必要はありません。

STEP4:破産審尋(裁判官との面談)※裁判所による
裁判所によっては、申立て後に裁判官と面談する「破産審尋」という手続が行われることがあります。裁判所の運用により、弁護士代理でも審尋が行われる場合があり、具体的な運用は裁判所や事件の事情によって異なります。
もし審尋が行われる場合でも、聞かれる内容は借金の経緯や現在の生活状況といった申立書の内容の確認が中心です。必ず弁護士が同席し、受け答えのサポートをしますので、何も心配はいりません。
STEP5:破産手続開始決定・同時廃止決定
裁判所が申立書類を審査し、問題がなければ「破産手続開始決定」と、それに続く「同時廃止決定」を出します。この決定が出た時点で、法律上は「破産者」となります。
同時廃止の場合は、この決定と同時に手続自体は終了するため、管財事件のように財産の調査や債権者集会が開かれることはありません。

STEP6:免責許可決定
同時廃止決定後、あなたの氏名などが国の新聞である「官報」に掲載されます。その後、約2か月の間に債権者から免責に関する意見がなければ、裁判所は「免責許可決定」を出します。
この決定が確定すると、法的に借金の支払い義務が免除され、経済的な再スタートを切ることができます。これが自己破産手続の最終的なゴールです。
自己破産のデメリットと手続上の注意点
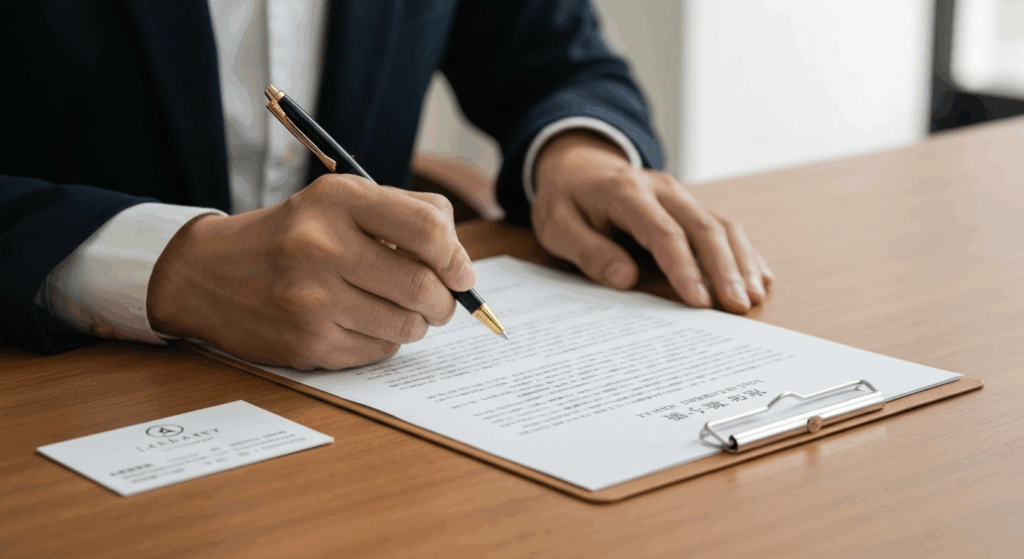
自己破産は借金問題を解決する強力な手段ですが、デメリットや注意点も存在します。
不安に思う点を正しく理解し、納得した上で手続を進めることが大切です。
一定期間、信用情報に登録される(ブラックリスト)
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
信用情報機関ごとに登録期間は異なりますが、登録されている間は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したり、誰かの保証人になったりすることが難しくなります。
これは生活再建のための重要な期間と捉えることもできます。
手続中は一部の職業・資格に制限がかかる
破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、一部の職業や資格に制限がかかります。
例えば、弁護士、司法書士、税理士といった士業や、警備員、保険募集人、旅行業務取扱管理者などが該当します。
ただし、この制限は免責が許可されれば解除される一時的なものであり、一生その仕事に就けなくなるわけではありません。
官報に氏名・住所が掲載される
自己破産をすると、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回、国の機関紙である「官報」に氏名と住所が掲載されます。
しかし、官報を日常的に確認している一般の方はほとんどいません。そのため、官報から自己破産の事実が周囲の人に知られる可能性は極めて低いと言えるでしょう。
【注意点】同時廃止の予定が管財事件になることも
当初は同時廃止での申立てを予定していても、裁判所の判断で管財事件に移行することがあります。例えば、申告されていない財産の存在が疑われたり、借金の理由(ギャンブルや浪費など)について詳しい調査が必要だと判断されたりした場合です。
そうならないためにも、弁護士に依頼し、申立ての段階で家計の状況や借金の背景について丁寧に説明する報告書などを添付することが非常に重要です。正直にすべてを話していただくことが、スムーズな手続への一番の近道となります。
自己破産に関するよくある誤解と正しい知識

自己破産には、世間のイメージからくる多くの誤解があります。
不安を解消するためにも、ここで正しい知識を確認しておきましょう。
誤解①:戸籍や住民票に記録が残る?
これは完全な誤解です。自己破産をした事実が、戸籍謄本や住民票に記載されることは一切ありません。
本籍地の市区町村役場が管理する「破産者名簿」には一時的に記載されますが、これも免責許可が確定すれば抹消され、一般の人が見ることはできません。
誤解②:選挙権がなくなる?
自己破産をしても、選挙権や被選挙権といった公民権がなくなることはありません。
これらは憲法で保障された国民の基本的な権利であり、経済的な理由で制限されることはありませんのでご安心ください。
誤解③:家族や会社に知られてしまう?
原則として、裁判所や弁護士からご家族や勤務先に連絡がいくことはありません。
そのため、ご自身で話さない限り、知られる可能性は低いです。ただし、以下のようなケースでは知られる可能性があります。
- 家族が借金の保証人になっている場合
- 会社から借金をしている場合
- 退職金見込額証明書などを会社に発行してもらう必要がある場合
ご自身の状況で周囲に知られるリスクがどの程度あるか、弁護士にご相談ください。
誤解④:すべての財産を没収される?
「自己破産=全財産没収」というイメージは誤りです。
法律で生活に必要な財産(自由財産)は手元に残すことが認められています。家具や家電製品など、生活必需品が差し押さえられることは基本的にありません。
誤解⑤:賃貸アパートを追い出される?
家賃をきちんと支払っている限り、自己破産したことだけを理由に賃貸アパートの契約を解除されたり、追い出されたりすることはありません。
ただし、家賃を滞納している場合は、その滞納家賃も破産の対象となるため、大家さんとの交渉が必要になることがあります。
要注意!自己破産しても支払い義務が残る「非免責債権」とは
自己破産をして免責許可決定を得ると、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなります。
しかし、中には例外的に支払い義務が残り続ける「非免責債権」というものが存在します。これらを知らずにいると、手続後にトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。
税金・社会保険料(年金、健康保険料など)
所得税、住民税、固定資産税などの税金や、年金保険料、健康保険料といった公的な負担は、国の財政の根幹に関わるため、自己破産をしても免責されません。
滞納している場合は、手続後も支払い義務が残ります。支払いが困難な場合は、管轄の役所に相談し、分割払いなどの交渉を行う必要があります。
養育費・婚姻費用
離婚した相手に支払う子どもの養育費や、別居中の配偶者に支払う婚姻費用なども非免責債権です。
これらは、家族を扶養する強い義務に基づくものであり、自己破産によって支払い責任を免れることはできません。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
他人を害する意図(悪意)をもって行った不法行為による損害賠償責任は、免責の対象外です。例えば、詐欺や横領で得たお金の返還義務などがこれにあたります。
罰金・科料など
交通違反の反則金や、刑事事件で科された罰金なども、国に対する制裁としての性質を持つため、免責されません。これらも自己破産とは関係なく、支払う必要があります。
自己破産でお悩みなら早川法律事務所へご相談ください

この記事では、自己破産の中でも多くの方が利用する「同時廃止」の手続の流れを中心に、デメリットや注意点、よくある誤解について解説しました。
自己破産は、決して人生の終わりではありません。むしろ、借金のプレッシャーから解放され、生活を再建するための法的に認められた前向きな手続です。
しかし、手続は複雑で、ご自身の状況に合わせた適切な判断が不可欠です。
もしあなたが借金問題で悩み、自己破産を少しでも考えているのであれば、一人で抱え込まずに、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
早川法律事務所は、千葉市で15年以上の実績を持つ法律事務所です。
- 弁護士歴15年以上の代表弁護士が、すべてのご相談に直接対応します。
経験の浅い弁護士や事務員任せにすることはありません。 - 千葉県内にお住まいの方であれば、オンラインでのご相談にも対応可能です。
借金問題は、早く相談するほど、取れる選択肢も広がります。